本日は本と旅行のお話しを。
今読んでいる本に文春新書から発売されている塩野七生さんの新刊「誰が国家を殺すのか 日本人へV」があります。その中でハタと納得する箇所があったのです。自分の旅を思い出しながら。
そのエッセイの中の「寄りそうだけで解決するのか」というタイトルからの抜粋です。

私には、地中海世界を舞台にした歴史エッセイをすべて書き終えた後ならばやってみたい、と思っていたことが三つある。
その一つに、若い頃にヨットを乗り継いでまわった地中海沿いの港町を、もう一度訪れるというのがあった。ところがその願いが夢で終わるのを、痛感している今日この頃である。五十年昔には可能であったことが今では不可能になったということだが、それは地中海世界の全域から、誰でも自由に安全に訪れることができるという意味での平和が失われてしまったからである。
しかもこの変化は、たかだかこの十年足らずの間に起こったことなのだ。私が「ローマ人の物語」を書き、すぐつづいて「ローマ亡き後の地中海世界」を書いていた頃までは、地中海に面した北アフリカ全域への旅行は安全だった。あの一帯には数多い古代のローマ時代の遺跡を歩きながら一人で半日過ごしても、心配するような事態にはまったく出会わなかったのである。近くの遺跡では欧米の大学の調査隊が発掘していて、彼らからもらう情報も役立った。
ところがこの十年で、すべてが一変した。ジャスミン革命とやらで独裁政権が次々と倒れたのはよいが、その後に残されたのは混乱だけ。遺跡でウロウロしているなどは許されなくなった。その辺の暴力団にでも拉致され、社会の混乱をよいことに浸透してきたISにでも売られるような事態になれば、日本政府だって出てこざるをえなくなる。まるで潮が引くように発掘隊が姿を消してしまったのも、学問的な関心が薄れたのではなく、この種の危険を避けたかったからにすぎない。
この一文を読んで、自分たちがチュニジアのチュニスを訪れたのが2010年の夏だったのです。呑気に家族4名です。高齢の母親と小学生低学年の娘を連れての個人での4人旅です。そんな滞在から4ケ月後にジャスミン革命は勃発したのでした。


その滞在では、日帰りで行けるチュニジアンブルーが美しい街「シディ・ブ・サイド」を観光し、呑気に帰り途中下車してカルタゴの遺跡を探しに行ったのです。さびれた海辺のレストランで食事したのも良い思い出。今はそんな呑気なことができないのだろうな。
チュニスに帰る電車の中では、乗客に囲まれ、どこから来たのかと問われ、日本と答えると、みんなで合唱してくれるは食べ物をくれるわで本当に陽気な楽しい時を過ごしたのでした。

チュニスの街も平和そのもの。街中にジャスミンを売る人々。ロコの人たちは男女共に耳にジャスミンを付けているのね。
そんな平和そのものの街で数カ月後に革命が起こるとは信じられなかったのです。
そんなことを思い起こさせてくれる塩野さんのこのエッセイだったのです。
人間行ける時に行かないといけないのね。コロナ直前に行ったペルーのマチュピチュも現在のペルーの国内情勢を考えると、簡単に行けないところになりました。
改めて世界が激動しているね。
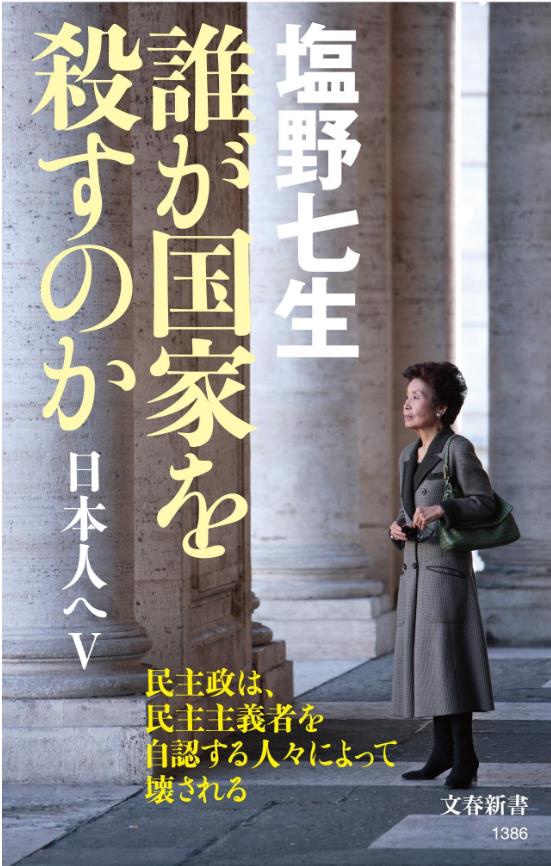
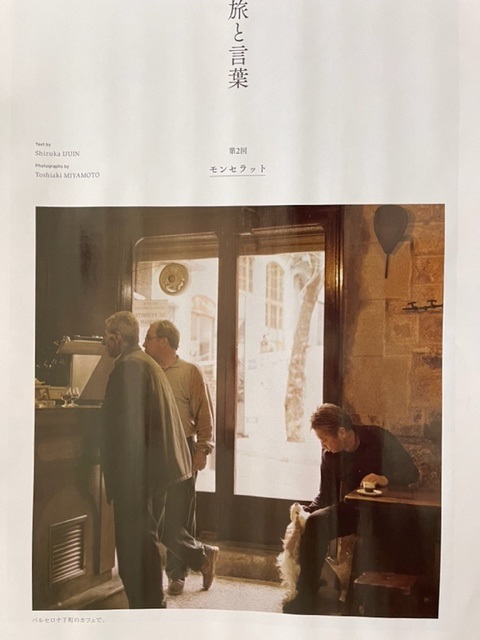




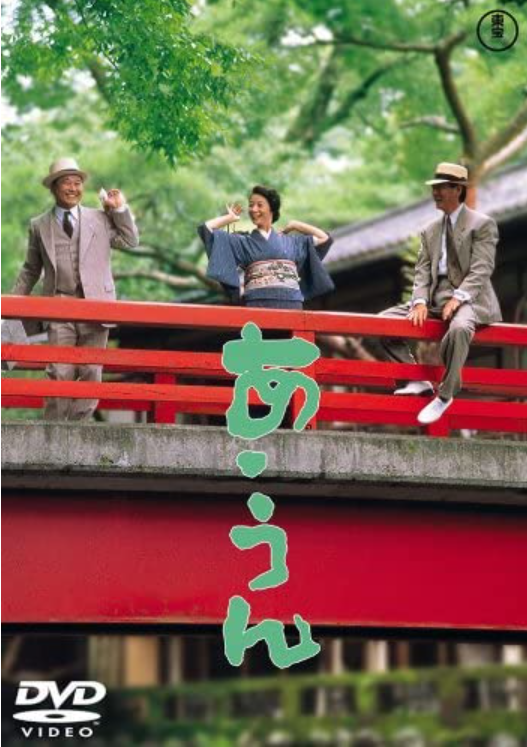




















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32706860.a0bbd9ef.32706861.8a0862ac/?me_id=1233984&item_id=10002008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffuusuis3%2Fcabinet%2Fjapan%2Fimg-japan-28.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
