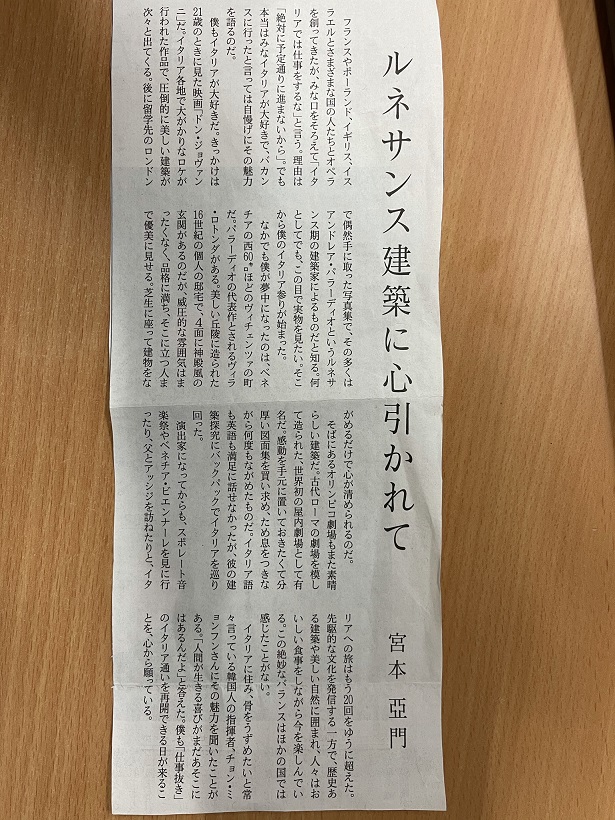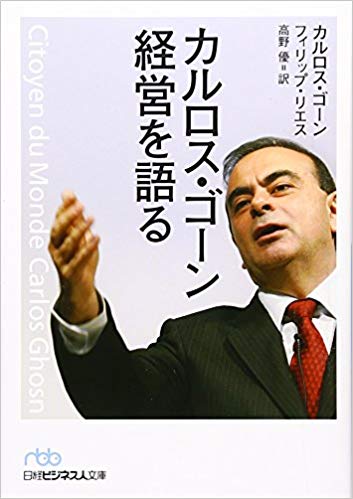2020年12月20日の日曜日の日本経済新聞の中面での、宮本亜門さんのエッセイに目が留まったのでした。タイトルは、「ルネサンス建築に心引かれて」というものです。

フランスやポーランド、イギリス、イスラエルとさまざまな国の人たちとオペラを創ってきたが、みな口をそろえて「イタリアでは仕事をするな」と言う。理由は「絶対に予定通りに進まないから」。でも本当はみなイタリアが大好きで、バカンスに行ったと言っては自慢げにその魅力を語るのだ。
僕もイタリアが大好きだ。きっかけは21歳のときに見た映画「ドン・ジョヴァンニ」だ。イタリア各地で大がかりなロケが行われた作品で、圧倒的に美しい建築が次々と出てくる。
(中略)
なかでも僕が夢中になったのは、ベネチアの西60キロほどのヴィチェンツァの町だ。パラーディオの代表作とされるヴィラ・ロトンダがある。美しい丘陵に造られた16世紀の個人の邸宅で、4面に神殿風の玄関があるのだが、威圧的な雰囲気はまったくなく、品格に満ち、そこに立つ人まで優雅に見せる。
(中略)
演出家になってからも、スポレート音楽祭やベネチア・ビエンナーレを見に行ったり、父とアッシジを訪ねたりと、イタリアへの旅はもう20回をゆうに超えた。先駆的な文化を発信する一方で、歴史ある建築や美しい自然に囲まれ、人々はおいしい食事をしながら今を楽しんでいる。この絶妙なバランスはほかの国では感じたことがない。
イタリアに住み、骨をうずめたいと常々言っている韓国人の指揮者、チョン・ミョンフンさんにその魅力を聞いたことがある。「人間が生きる喜びがまだあそこにはあるんだよ」と答えた。僕も「仕事抜き」のイタリア通いを再開できる日が来ることを、心から願っている。
実は、自分も旅先はイタリアが一番好きなのです。記録を見ると、2004年の夏に訪れたのが初めてかな。以来、7-8回は通っていると思います。
そして、一番好きな町がベネチアかな。シチリアのエキゾチックさ、アマルフィの絶景もよいけど、ベネチアのサンタルチア駅を出ると、すぐに運河というシチュエーションには参るんだな。



そんなイタリアですが、トラブルもよく起こるのです。一度、ローマのテルミニ駅周辺のホテルに宿泊した時には、ベルボーイに預けたスーツケースが誰かに盗まれたのでした。
小学校に入学したての長女が私の母のスーツケースを転がしながら、ホテルから出て行った人を見たというのです。そして、正式な紛失証明書をもらうために、イタリア中央警察まで出向いたことがあるのです。対応してくれた警察官は、何も聞かず、サインだけして証明書をくれたのです。こんなの日常茶飯事だというように。

ある時は、チュニスからシチリアへフェリーで渡り、深夜12時にタクシーなどが全くいない港で降ろされたのでした。町の中心部まで歩くこと30分。バーでタクシーを呼んでもらい、トラーパニからパレルモまでタクシーで3時間ほど高速をぶっ飛ばしたのです。3万数千円の料金をとられ、財布にも痛い出費でした。
そんなトラブルにも多々遭遇する国ですが、やはり愛すべきお国なのですね。
自分はいついけるかな。